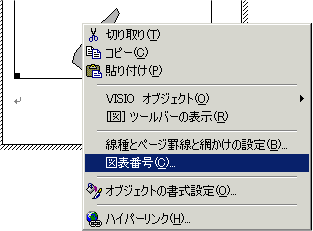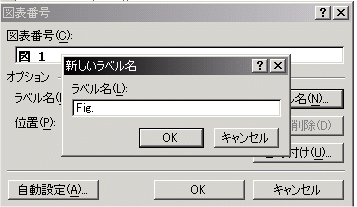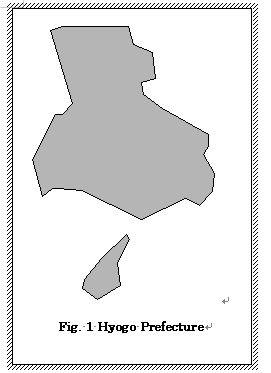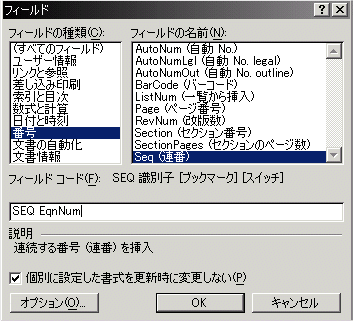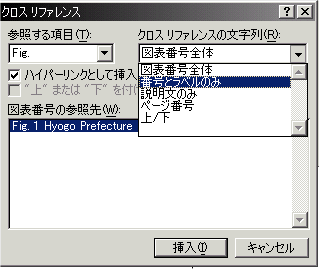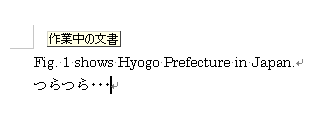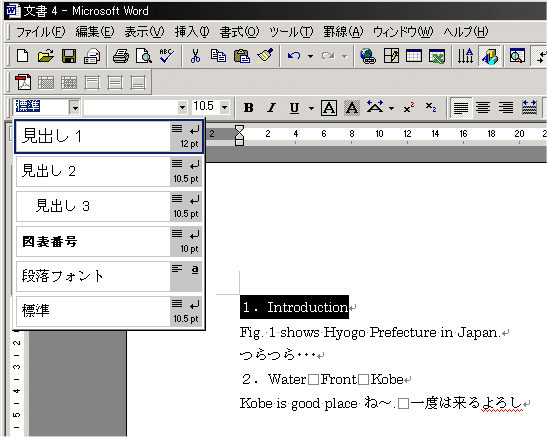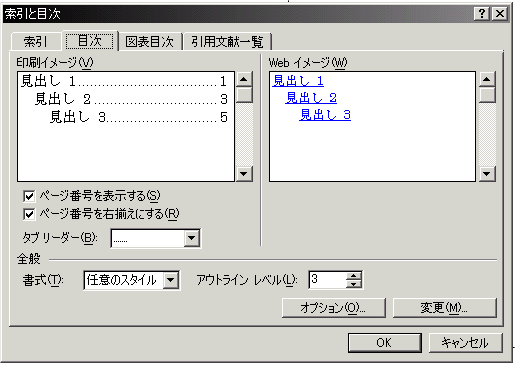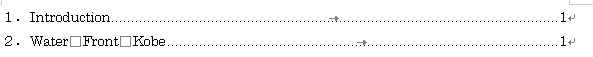相互参照
1.相互参照って・・・?
この章では相互参照について書きますが、相互参照と聞いて皆さんピンとくるでしょうか?要は数式や図表番号と本文中のそれに対応した番号を互いに対応させる、参照させるということ。そんな面倒なこと手動でやってられないですもんね。TeX使いの方は馴染みがあると思いますけど・・・。\labelつけて\refで呼び出して・・・。Wordでもよく似たことができます。実わ・・・^^。びっくりくりくり。ここでは数式番号と図表番号に関してのみ書きますが、ページなども大丈夫みたいです。
2.数式番号・図表番号の振り方
数式番号や図表番号を相互参照させるには、普通に番号振ってはいけません。フィールドを使います。どちらもどうようのやりかたでできるので図表番号について説明します。「挿入」-「図表番号」か図を右クリックして「図表番号」を選択します。
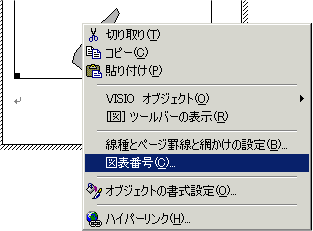
するってーとこんなウィンドウが出てきます。付けたいラベルを選んでO.K押します。以上。

デフォルトでは番号が「選択した項目の下」になってるので表のときは上にしておきましょう。それから、つけたいラベル名が無かった場合、「ラベル名」のボタンをクリックすると自分でラベル名がつけれます。ここではFig.とつけてみました。
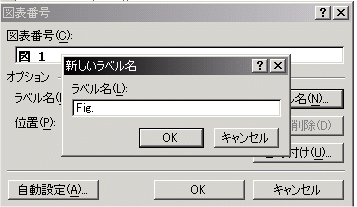
という具合にしていけば、ラベルがつきます。後は図の名前でもつけてください。中央揃えにでもすれば綺麗につきます。
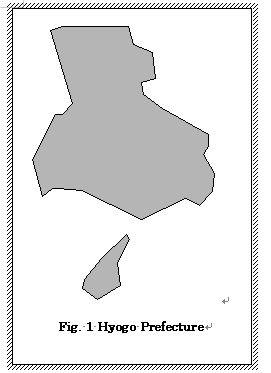
ただ、数式の場合、Eq.1など文字をつけずに番号を振りたい場合があります。特に学会などでフォーマットが決まっているときとか。そういう場合は「挿入」-「図表番号」からではなくて「挿入」-「フィールド」から「番号」-「Seq(連番)」を選ぶとよいでしょう。そして下のフィールドコードの欄に識別子を書きます。これは連番の種類を表すもので、なんでもいいです。ここでは数式なので「EqnNum」という識別子を付けてみました。
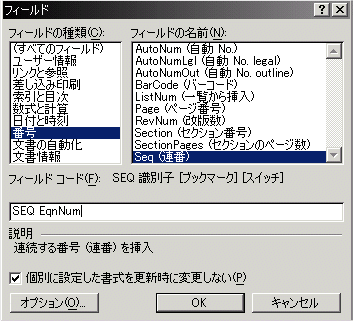
申し訳ないことにこの方法で番号を振ったときにどうやって相互参照するのか知りません。おそらくブックマークつけてなんかするのかなーって感じですけど、分かったらお知らせいたします。更新をお楽しみに・・・。ていうか、知ってたら教えて♪
3.相互参照の仕方
相互参照するには「挿入」−「クロスリファレンス」からウィンドウを開きます。
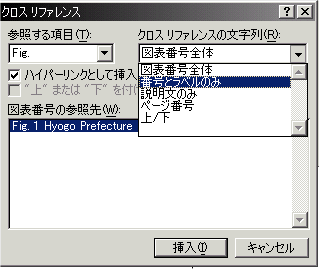
で、参照する項目で先ほどの「Fig.」を選び、図表番号の参照先からさっきのFig.1を選べば挿入できます。注意としてはクロスリファレンスの文字列を「番号とラベルのみ」にしとかないとHyogo Prefectureまで入ってしまうのであしからず。見ての通り、これを使うと図表のページ番号も参照できるので「Fig.1(P.1)の〜は・・・」みたいなちょっと凝ってそうなこともできてしまいます。
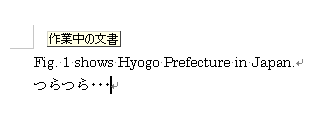
出来上がり♪蛇足ですが、この方法ではFig.1はハイパーリンクみたいなことになってます。上の画像ではマウスが移ってないんですが、Fig.1の上にあるマウスが指になっててクリックするとFig.1へ画面が飛んでいきます。これはPDFにしても残っている機能です。要らんといえば要らんが・・・。変なところがんばるなーマイク!全部書くのもうぜーぜ!マイクよぉ〜!
4.目次の相互参照
目次を作るのってだるくないですか〜。TeXなら一撃でできますよー。でも、実はWordでもできるんですねー。びっくり!作り方はいたって簡単。章や節の文字列の文字の種類を「標準」から「見出し」に変えます。
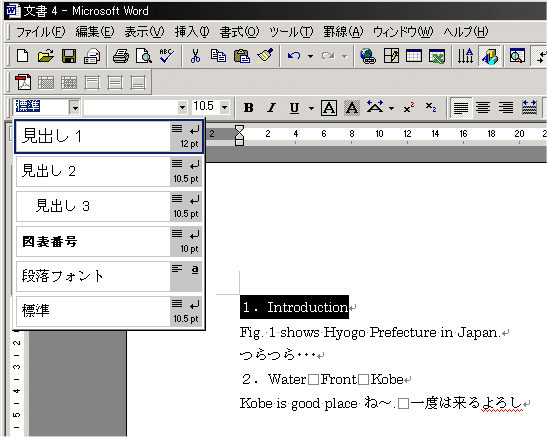
見出しに変えたら、「挿入」−「索引と目次」でウィンドウを開き、目次のところでテケテケと設定すれば、一撃で目次ができます。アウトラインレベルがおそらく見出しの何番目まで目次に入れるか、という設定でしょう。使ったこの無いもんで^^
お気づきとは思いますが、同じウィンドウで図表目次やらなんやらも作れます。索引作るときは「挿入」-「フィールド」で何か挿入したらいけると思いますが、やったこと無いのでよく知りません。あしからず。
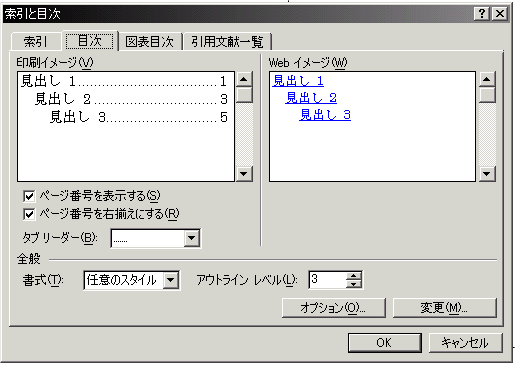
という感じで作ってみたのが下図。簡単でしょ。
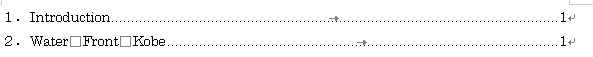
←図表 ショートカット→
WordTopへ OfficeTopへ